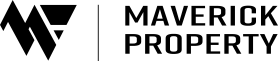不動産相続におけるご相談
- ホーム
- 不動産相続におけるご相談
相続にともなう不動産売却も
ご相談くださいinheritance
遺産相続で問題になりやすいのが家やマンションなど不動産の取り扱いです。とくに複数の相続人がいる場合にはトラブルとなりやすいもの。こちらでは、大阪市の不動産売却や買取を行う「株式会社マーヴェリックプロパティ」が、不動産相続時に押さえておきたいことや相続時のトラブル相談事例をご紹介します。
初めての不動産相続で
知っておきたいことinheritance
遺産相続では相続財産と相続人を確定したら、相続人全員で分け方を決めなければいけません。現金や預貯金であれば分割は難しくなく、1円単位で法定相続分に従って分けることが可能です。
しかし不動産についてはお金と異なり、細かく分けることはできません。不動産の相続分を決める際には、現物分割、代償分割、換価分割、共有の4つの方法から選ぶ必要があります。

現物分割 そのままの形で引き継ぐ
不動産などの相続財産を現物のまま、形や性質を変えないでそのまま相続人に受け継ぐ方法です。たとえば親の遺産を相続する際に、土地や建物を長男が相続し、残りの預貯金を長女が相続したりします。
そのままの形とはいえ、土地の場合は法定相続分と同じ割合に「分筆」して相続することも現物分割のひとつです。なお、分筆できるのは土地だけであり、建物部分を分筆することはできません。
現物分割は不動産を売却しないので、手間がかからず、相続手続きがシンプルになる点がメリットです。一方で、財産の価値に偏りが生じて不公平になりやすく、場合によっては遺産分割協議がまとまらない恐れもあります。
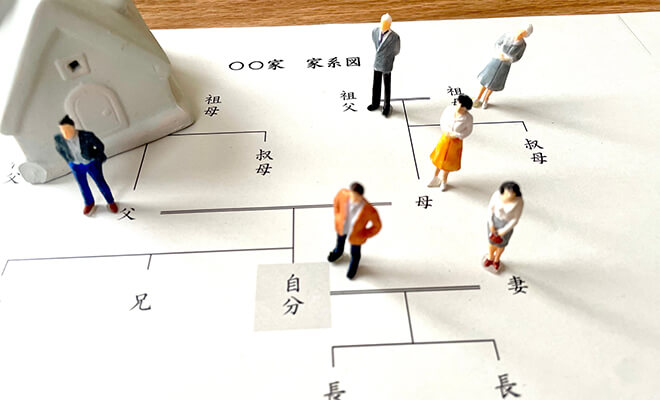
代償分割 代償金を支払って解決する
相続人のひとり、または数人が法定相続分を超える財産を取得し、他の相続人に対して、法定相続分を超えた分に応じた代償金を支払う形で遺産分割を行う方法です。
たとえば相続人が2人で、相続財産のほとんどが2,000万円の実家のみの場合、ひとりが家を相続し、他の相続人に対して、1,000万円の金銭を支払うことによって遺産分割を行います。金銭によって細かく調整できるので公平に分配でき、不満が出にくい分け方です。
ただし不動産には定価がないため、相続財産の価値を評価する方法でトラブルになるケースがあります。どの相続人も納得する評価方法を適用し、さらに相続した人には代償金を支払うだけの資金力も必要です。

換価分割 売却したお金を分け合う
相続した不動産を売却し換金してから、相続人の間で金銭を分配する方法です。代償分割の例のように相続財産のほとんどが2,000万円の実家のみの場合、実家を売却して得た金額から諸経費を差し引き、残ったお金を法定相続割合に応じて分け合います。
代償分割と同じく、金銭で細かく調整できるので、不公平になりにくい分け方です。しかも代償分割と違って実際に売却するので、不動産の評価方法について揉めることはありません。また、相続した人が代償を支払う資金を用意する必要もありません。
デメリットとしては、売却先を見つけて実際に売却するまでに時間や手間がかかってしまう点です。売り急ぐあまり、安値で売却することになるかもしれません。何より実家を手放す場合は、寂しく思う相続人もいるでしょう。

意見が合わない場合は調停・審判
現物分割、代償分割、換価分割のほかには、相続財産を法定相続分で共有するという方法もあります。しかし共有した物件がさらに相続されると、権利関係が複雑になってしまう恐れがあり、おすすめできる方法ではありません。
なお、遺産分割協議がまとまらなければ、最終的には家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることになります。調停で合意できなければ、審判という手続きになり、家庭裁判所が分配方法を決定します。
相続人の間で話がまとまらず、争いに発展してしまうような遺産分割は故人が望むところでもないでしょう。こうした事態に陥らないように、あらかじめどのような相続が適しているのかシミュレーションしてみるのもおすすめです。
相続に関する当社ブログ
相続登記の義務化についてinheritance
「相続登記」とは、不動産の相続において必要な手続きのひとつです。これまでは罰則がなかったため、多くの方が手続きせず、所有者不明の不動産が大量に増えてしまいました。
この問題に対処するため2024年4月1日から施行されたのが相続登記の義務化です。不動産の所有権を相続したことを知った日から3年以内に相続登記を行うことが、法律上の義務になりました。正当な理由がないのに相続登記をしない場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。
よくあるトラブル例
- 事例 1遺言書がない
-
遺言書があれば、遺産の内容がすべて書かれてあることが多く、遺言書の内容に沿って相続財産を分配できます。相続人を確定したり、相続財産を探したりといった手間や時間が不要になります。
遺言書がなければ、遺産がどこにどれくらいあるのかリストアップすることから始めなければいけません。さらに遺産分割の方法を相続人全員で話し合わなければいけないのです。当人同士の話し合いだけでは、どうしても揉めやすくなります。
- 事例 2相続人が複数いて、共有持分で
相続しようとしている -
売却活動の動き出しから完了(現金化)に至るまで、通常の売却よりも時間と手間がかかります。相続人が複数いらっしゃる方で、共有持分で相続しようとお考えの方は、相続してからが大変なので、手続きをする前にまずはご相談ください。
- 事例 3分割方法およびその割合で揉める
-
土地を相続した場合など、法定相続分と同じ割合で分割して相続することもあります。これは「分筆」という現物分割のひとつですが、財産の価値に偏りが生じて、不公平になりやすいというデメリットがあります。
また単純に面積で等しく分けるだけでは、土地が小さくなりすぎることもあります。接する道路との関係で、建物を建てられなかったり、いびつな形になったりすることも。せっかく相続した土地をうまく活用できず、遺産分割協議がまとまらなくなる恐れもあります。
- 事例 4コストが発生する
-
相続した不動産を活用も売却もせず、とりあえず持ち続けていても、何も生み出さないばかりか固定資産税などの税金がかかってしまいます。また不動産の劣化スピードを抑えるためには、管理費用や整備費用がかかります。
さらに、こうした整備を怠って、建物の劣化が進み景観を著しく損ねる状態になると、「特定空き家」に指定され、行政から助言や指導、勧告を受けることもあるのです。特定空き家の指定は、固定資産税がはね上がったり、解体費用を請求されたりすることにもつながります。
- 事例 5名義変更を行っていなかった
-
2024年以前、相続時の名義変更は義務ではありませんでした。しかし名義変更がなされていない物件は、そのままで売ったり建物を建てたりできません。相続登記が遅れれば遅れるほど、だれが相続人なのかわかりにくくなり、いざ登記しようとしても煩雑なことになってしまいます。
こうした問題に対処するために法改正されたのが2024年4月の相続登記の義務化です。不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記をしなければいけません。これを怠ると、10万円以下の過料が課されることがあります。
- 事例 6相続税支払いの原資とは?
-
相続税は原則として現金で一括して納めなければいけません。しかも相続税の納付期限は相続開始から10ヶ月以内であり、あっという間に期限がやってきます。相続財産の大半を不動産が占めていると、現金での支払いが難しくなることがあります。
相続税支払いの原資が不足する場合、年払いによる延納、現物による物納、不動産の売却代金による納付、金融機関からの融資、相続放棄などの対応があります。いずれの方法にもメリット、デメリットがありますので事前に対策を考えておきましょう。
- 事例 7相続した土地が底地だった
-
「底地」とは借地権が設定されている土地のこと。底地の地権者が亡くなり相続した場合、借地契約がなくなるわけではありません。設定された借地権はそのまま残り、地代収入をそのまま引き継ぐことができるというメリットがあります。
しかし底地を相続すると、土地を所有していることにはなりますが、自由に使うことはできません。土地を使う権利は借地権者にあるからです。このように底地は通常の土地に比べて権利が制限され、扱いに難しい物件であり、注意が必要になります。
不動産相続の手続きに
かかる主な税金・費用inheritance
相続手続きにかかる税金と費用のうち、もっとも負担が大きくなるのは相続税です。しかし財産を相続した場合に必ずかかるわけではありません。基礎控除を超える場合に発生し、実際に相続税を支払う人は全体の1割もいないといわれています。
とはいえ、相続税の申告期限は遺産相続発生を知った日の翌日から10ヶ月以内です。いざというときにあわてなくて済むように、事前に情報を仕入れておきましょう。
| 項目 | 概要 | 負担額の目安 |
|---|---|---|
| 相続税 | 財産が基礎控除を超える場合にのみかかる | 控除分を超える額に応じて、10%~55%の税金 |
| 登録免許税 | 相続登記(不動産の名義変更)にかかる税金 | 固定資産税評価額×0.4% ※例外的に2.0%の場合 |
| 必要書類の取得費用 | 登記手続きに必要な書類を取得するための費用 | 3,000円程度~ |
| 司法書士手数料 | 登記手続きを司法書士に依頼した場合の手数料 | 5~10万円前後 |